#バブル界隈|Z世代があこがれるバブル。それは、何だったのか?
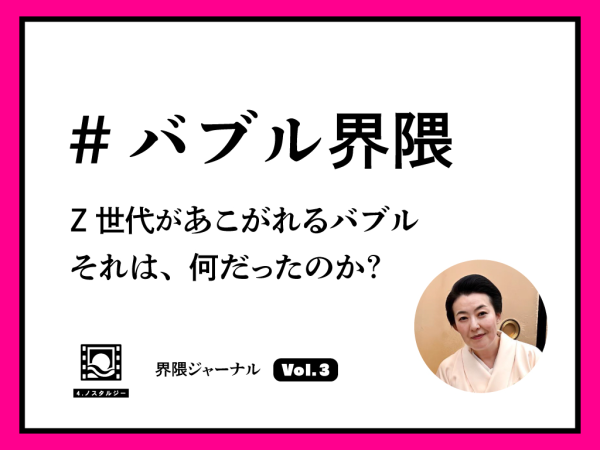
全てが“ファンタジー”だった——バブル時代
昨年10月にNHKで放送された竹内まりやの特番の中で、ゲストのピアニスト 角野隼斗(Z世代・1995年7月生まれ)がバブルへの憧れを
「バブル期にファンタジーを感じている。冷たさの中に温かさがあり、普遍的なものがあると古さを感じなくなる」と述べていた。
近年、日本のシティポップが世界中のZ世代に人気を集めているのだが、バブル時代(1986年12月〜1991年2月)をほんの少しだけ味わった筆者として、その時代の雰囲気を振り返ってみたい。

なぜZ世代はバブルに魅せられるのか?
戦略コンサルティングファームのマッキンゼー・アンド・カンパニーは、Z世代を1990年代後半から2010年頃に生まれた人々(2025年時点では10代前半から30歳)と定義しており、世界の人口の4分の1を占める。
幼少期にITバブル崩壊後の経済停滞、リーマンショック、東日本大震災といった不安定な時期を経験。そのため、経済面では保守的で、現実的な生活を重視し、安定を求める傾向が強い。
一方で、低金利な銀行ローンの一括提案依頼サイト「ロンたす」が実施した『Z世代のバブル景気に対する意識調査結果』では、バブルに対して「日本中が景気に沸きキラキラした世界」というイメージを持つ人が半数以上を占める。

低金利で借り、投機する狂乱の時代
では、「Z世代」が注目する、「バブル期」とは、どんな時代だったのか?
バブル発生の主な要因
❶「プラザ合意」(1985年9月22日)による円高
~プラザ合意直前の1ドル=240円台から、わずか1年で1ドル=150円台に~
40年前、日本は円高により輸出は不利になり、国内景気が低迷。一方で、海外生産中心の企業は円高の恩恵を受ける。徐々に景気が回復し、企業はカネ余りの状況に。
❷日本銀行の金利引き下げ
~政策金利を5%(1985年)から戦後最低の2.5%(1987年)に引き下げ~
国内景気の低迷解消対策として金利を引き下げ。銀行からお金を借り、投機の時代に。銀座では「地価は決して下落しない」という土地神話が生まれる。
不動産取引は加熱し「山手線内側の土地の価格で米国全土が買える」と揶揄されるほど地価が高騰した。

画像:Wikipedia commons: Plaza Hotel May 2010
世の中が一気に浮かれた時代に
カネ余りと投機で狂騒の幕が開き、企業の交際費は右肩上がりに増加。1980年代の10年間で年3兆円規模から、ピークの1992年には約2倍の6.2兆円に達する。
今回、当時を象徴する事例を少し紹介しよう。

ディスコブーム
TBSのドラマ『不適切にもほどがある』の第5話に「マハラジャ」が登場し、当時のディスコの様相が描かれたことで再び注目を集めたのは記憶に新しい。ディスコの中でも「ジュリアナ東京」はバブルを象徴する場所として特に有名だった。ちなみに「マハラジャ」の名付け親は、あのデヴィ夫人である。
クリスマスの高級ホテルブーム

全室角部屋でモダンなデザインの「赤坂プリンスホテル」は、クリスマスをカップルで過ごす場所の代名詞。中には、帰り際に翌年の予約を入れる強者も・・・
女性へのプレゼントとして流行したのは、ティファニーのオープンハート。街にはティファニーブルーの紙袋を手にして颯爽と歩く女性たちがあふれていた。
画像:Wikipedia commons 解体前の赤坂プリンスホテル 投稿者(Wiiii)
タクシーは1万円札をふって止める
接待が盛んで、帰りはタクシーチケットが渡され、銀座などの繁華街ではタクシー争奪戦が繰り広げられる。タクシーを捕まえたいあまり、1万円札を振ってタクシーを止める人々が登場。当時、私は彼らを札振り戦隊「マンレンジャー」と命名する。
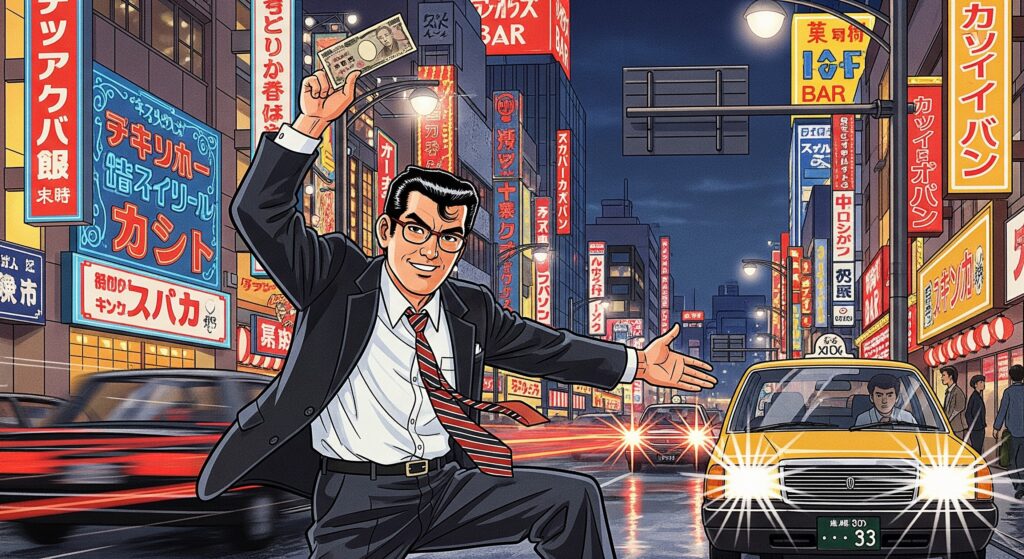
モノとカネがあふれ、街も人も浮かれていたバブル期は、まるで異世界のような活気に満ちあふれていた。しかし、そんな異世界が永遠に続くはずもなく1991年に崩壊。Z世代にもつながる、「失われた30年」が始まるわけだ。
Z世代がバブル時代にあこがれるのは、不安定な現代を生きる中で、過去の豊かな時代に抱いた「自由に消費できる楽しさ」や「華やかな日常」を疑似体験したいという願望の表れかもしれない。
記事:研究員 佐々木倫子
【主な参考資料・出典】2025年9月30日閲覧
※本記事は上記資料に加え、関連メディアの公開情報を対象としたデスクリサーチ(編集者調べ)に基づき作成しています。
※ 本投稿はWEシンクタンク「日本ロマンチスト協会」の発表内容からの転載です。



