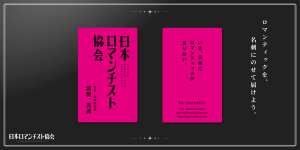はこだて国際科学祭で「海ノ民話」を語りました——海のめぐみと物語の力

ワールドエッグスの吉田さおりです(^▽^)/
海ノ民話のまちプロジェクトでは、日本各地に伝わる海にまつわる民話をアニメ化し、アーカイブするとともに、そのアニメを活用・PRすることを推進しています。
先日、「はこだて国際科学祭」に弊社代表の波房とともに登壇し、座談会「『海ノ民話』から学ぶ海のめぐみ」でお話ししました。はこだて国際科学祭は北海道函館市で2009年から続く、科学を身近に感じてもらうための市民参加型イベントです。
登壇者・プログラムの詳細は公式ページをご覧ください▼
https://sciencefestival.jp/event/2025_minwa/
上映とディスカッションの概要
「海ノ民話のまちプロジェクト」の概要と今後の展望について、当プロジェクトの統括プロデューサーである波房が説明。当プロジェクトで制作した北海道の海ノ民話アニメーション2作品―― 「ムイとアワビの合戦」(函館市)と「折居ばあさんと鰊」(江差町)――を上映し、海のめぐみと物語の可能性を多角的に語り合いました。
冒頭、国立文化財機構 東京文化財研究所・石村智さんから、民話は人が語り継ぐことで存続する「無形文化遺産」であり、「人がいなければ存在できない」という示唆がありました。アニメという“かたち”を得ても、語りの主体である“人”が関わり続けることが大切だと、あらためて実感しました。

『ムイとアワビの合戦』(函館市)
まずはアニメを上映し、函館出身の私から作品を紹介しました。主なポイントは次のとおりです。
- ムイ(オオバンヒザラガイ)とアワビの争いの話は、230年以上前にはすでに口伝されていた。
- ムイは寒流、アワビは暖流の生き物で、海流が交わる豊かな海を表している。
- 物語の舞台「武井(むい)の島」を境に、数十年前までは生息域の住み分けが見られたが、近年は海水温上昇の影響か混在し、アワビが増えている。
- このアニメを通じて、地域の民話だけでなく函館の海の生態も学べる。

『折居ばあさんと鰊』(江差町)
上映後は江差町教育委員会の小峰彩椰 学芸員が解説。示唆に富む内容でした。
- 舞台のかもめ島は現在は陸続きだが、昭和初期までは舟で渡っていた。
- 折居ばあさんが海に流した液体で白く濁る描写は、ニシンの産卵「群来(くき)」の表現。
- 江差の浜には、甕を逆さにしたような形の「瓶子岩(へいしいわ)」がある。
- 物語で折居ばあさんの後に残されたとされる仏像は、北海道最古の神社「姥神大神宮」に祀られている。

海のめぐみと歴史からの示唆
石村さんによれば、北前船交易の主要輸出商品はアワビ・コンブ・ニシン。とくにニシンは食用ではなく、肥料(干して粉末化)としての需要が大きく、乱獲が不漁を招いたといわれます。近年は漁獲量が回復傾向にある一方で、必要な分だけをいただくという折居ばあさんの網の教えを、現代の海洋資源利用に重ね合わせたくなります。

“棲み分け”と“来訪神”という視点
学習院大学・久保華誉先生からは、陸域の昔ばなしに見られるキツネとタヌキの棲み分けの例や、折居ばあさんを来訪神として読み解く見方が示されました。
来訪神は常に在す神ではなく、時を定めてやって来る神。秋田のナマハゲや宮古島のパーントゥなど、ユネスコ無形文化遺産に登録された事例もあります。もし折居ばあさんが江差に恵みをもたらす来訪神だったとしたら、仏像へと“化して”祀られるほど町に愛着を持った存在だったのかもしれません。

昔ばなしの「どこでも」、海ノ民話の「ここ」
昔ばなしは時と場所を特定しないのが大きな特徴です。
一方、海ノ民話アニメーションは場所(場合によっては時代も)を特定し、地域のアイデンティティを作品に刻みます。だからこそ、教育・郷土愛の醸成・観光・防災など、幅広い場面での活用が可能です。そのためにも、地域の方々が作品を観て語り合う場が重要だと考えています。
今回の座談会は、異なる立場の視点が交わる「語りの場」となりました。物語が人を介して受け継がれるように、海と地域の未来を考えるヒントもまた、人の対話から生まれるのだと感じています。